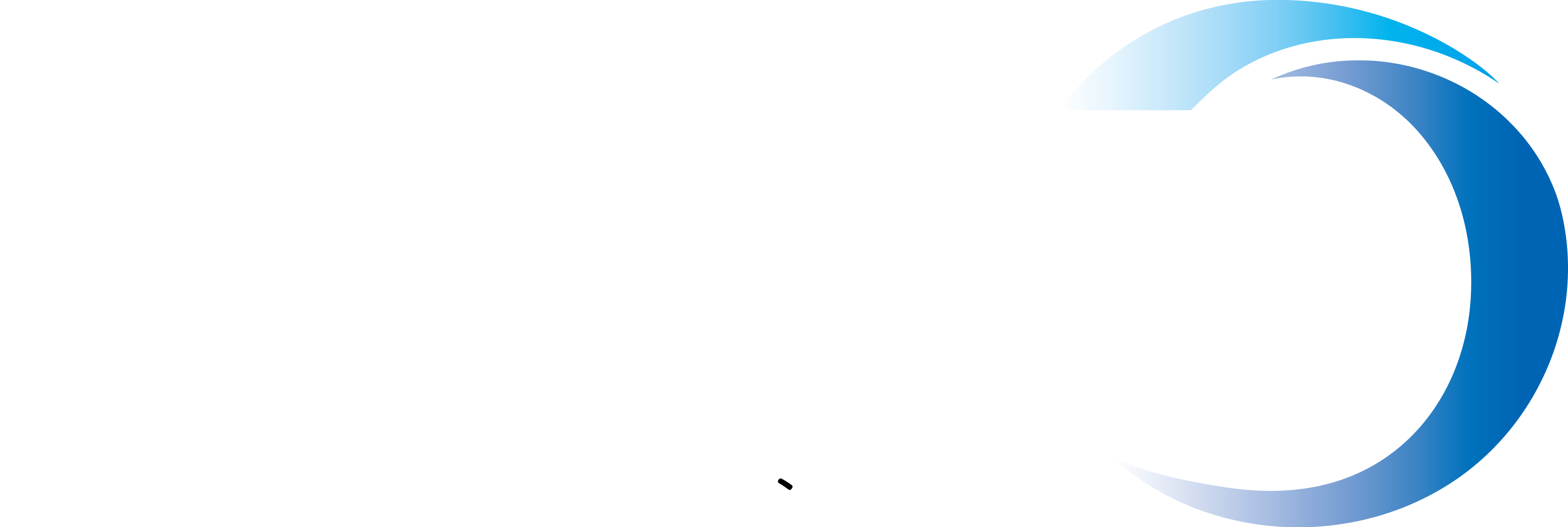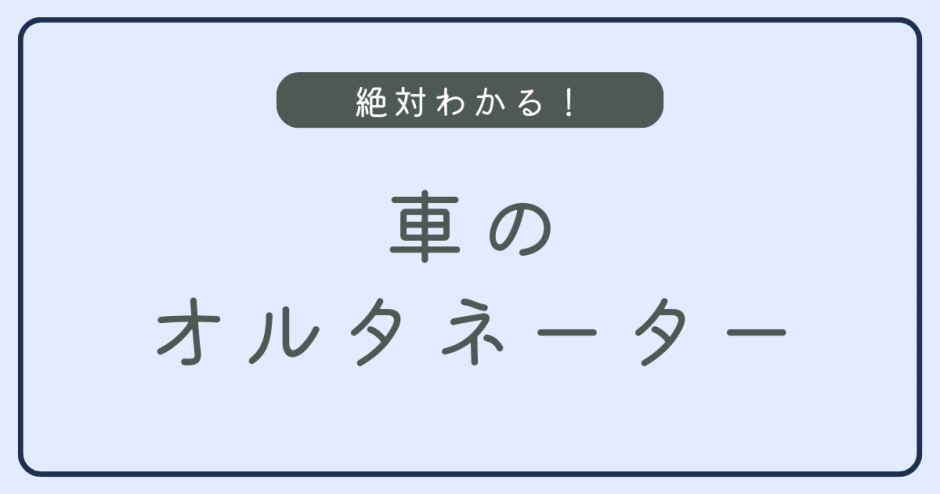名前は聞いたことがあるけれど何?と感じる車のオルタネーター。
誰でもわかるように解説します!

- 車のことはパートナーに任せているのでわからない
- 今さらオルタネーターのことを聞けない
- 車の調子が悪いので車屋さんに持って行きたいけど、基本的な情報は押さえておきたい

オルタネーターに関する疑問はこの記事で解決できます!
目次
車のオルタネーターとは
車のオルタネーターは「発電機」の役割をしています。
車を使用する時、カーナビやエアコン、ヘッドライト、ウィンカー等電気を使用します。
上記のカーナビなどの装置はまとめて電装品や電装系と呼ばれます。
電装系に電気を送っている(供給している)のがオルタネーターです。
オルタネーターはエンジンと連動して動き、発電し、電気を供給しています。
そのため、停車中はオルタネーターが電気を作って供給することができません。
停車中に電気を供給しているのは「バッテリー」と呼ばれる部品です。
バッテリーは聞いたことはありますか?
バッテリーは車の蓄電池です。
オルタネーターは、エンジンが動いている時に発電して電気をつくり、電装品やバッテリーに電気を供給します。
バッテリーは蓄電池なのでオルタネーターが作った電気をバッテリーに貯めています。
停車中に電装品に供給したり、エンジンをかける時にバッテリーに溜まった電気を利用して、エンジンの始動をします。
車のバッテリーについては以下の記事も参考になります。
オルタネーターはどこにある?
オルタネーターはほとんどボンネットに入っていて、エンジンの本体の近くにあります。
この記事を読んでいる方はあまりボンネットを開けたりすることはないかもしれませんが、オルタネーターはパッと見ただけではどれ?と思うことの方が多いかもしれません。
以下はマツダのMPVのボンネットを開けた写真です。

マツダのマークがついている部品がエンジンです。
赤丸のところにオルタネーターが入っています。
パッと見ただけではわかりにくいので、近に寄った写真を紹介します。
マツダMPVの場合、オルタネーターはエンジンをほぼ真上から見てやっと見える程度です。

人が見ようと思って見える程度なので、わかりにくい場所に設置されている車が多いです。

ボンネットを開けて見る程度では、故障している等はわかりにくいケースがほとんどです。
オルタネーターの調子が悪くなる兆候は音で感じることができ、車に詳しくない人でも判断できます。
オルタネーターが故障するとこんな症状が出る
オルタネーターの不調は最初に異音がし始め、異音を放置しておくと、そのあとに何かの症状が出ることが多いです。
順番に紹介していきます。
オルタネーターの不調は最初に異音がすることが多い
オルタネーターの不調や故障に気が付く一番最初のサインは、走行中の異音です。
オルタネーターは、エンジンと連動して電気をつくる部品であるため、走行中またはアイドリング中に異音がします。
もし異音に気が付いたときは、ボンネットを開けてみてどこからなっているか確認してみましょう。
異音は主に以下のような音です。
- キーキーやキュルキュル
- カラカラやカリカリ
- ウィーンやヴ―
キーキーやキュルキュルはベルトの不調
オルタネーターは動かすために部品の一部にベルトが付いています。
キュルキュルするような音がする場合は、オルタネータ―のベルトが劣化している可能性があります。
ベルトが劣化すると、オルタネーター本来のパワーを発揮することができず発電不足になります。
ベルトはゴム素材でできているため、硬くなったりひび割れたり、伸びてゆるんだりします。
ベルトは劣化して切れてしまうと、車を走行させること自体が不可能になるためベルトの交換を行います。
ベルトは正常でも、張りが不足しているケースがあります。
張り不足の場合は、修理の際、張りの調整をしてもらいます。
オートテンショナーと呼ばれる、自動でベルトの張りを調整してくれる装置が付いているオルタネーターもあります。
オートテンショナーが付いている場合は、装置の劣化の可能性があるため、部品の交換をする流れになることが多いでしょう。
カラカラやカリカリはプーリーの不調
アイドリング中や、走行中の異音が「カラカラ」や「カタカタ」などの場合、大きな事故に発展する可能性があるため早急の修理をおすすめします。
カラカラ等の音がする場合、ベルトがかかっている「プーリー」と呼ばれる部品の劣化が考えられます。
プーリーが劣化していると、オルタネーターのベルトが外れてしまい走行ができなくなったり、オルタネーター本体からプーリーが外れて他の部品も傷つけてしまう等が考えられます。
走行中に運転手の意図に反して急停車してしまうことが起こり得るため、もし気が付いたときは安全な場所に停車し、エンジンも停止させるようにしましょう。
移動はロードサービスに依頼するなど、レッカーで移動することが多くなるケースです。
ウィーンやヴ―はベアリングの不調
エンジンをかけている時に、急に「ウィーン」や「ヴ―」という音が絶えずするようになるケースがあります。
ウィーンやヴ―などの音の場合は、オルタネーターの中のベアリングの劣化等の可能性があります。
ベアリングは、機械のなかの軸をなめらかに回転させる部品です。
引用元:株式会社NTN
ベアリングはオルタネーターの回転の軸についている部品です。
アクセルを踏んでエンジンの回転数が上がるとウィーン等の音も連動して大きくなったり、早くなったりします。
音が鳴りだした最初の頃はオルタネーターの発電能力に影響がないため、放置してしまうケースがあります。
ですが、時間が経つにつれて音が大きくなったり、その他の悪影響が出る可能性があります。
いつもと違うかも?と感じたら、車屋さんなどに相談してみましょう。
オルタネーターの異音を放置していると故障の症状が出る
いつもと違うなぁと感じていても、オルタネーターの異音を放置していたり、まだ大丈夫かなと気にしていなかったりすると、車に症状が出て、オルタネーターの故障につながります。
できれば症状が出る前に、車屋さん等に相談することをおすすめします。
もし、そのまま放置していると以下のようなことが起こります。
- バッテリーの警告灯が点灯する
- エアコンやウィンカーなどの電装系が不安定になる
- ハンドルが重くなる(パワステが効いてない)
- エンジンの振動が不安定になる
それぞれ解説していきます。
バッテリーの警告灯が点灯する
オルタネーターの異音を放置し、不調があると、バッテリーの警告灯が点灯します。
警告灯は運転席のスピードメーターの中のどこかに設置されていて、以下のようなマークです。
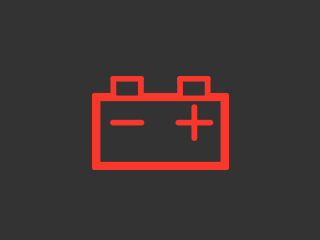
バッテリーの警告灯のマークは、世界共通のマークのため、日本車、外車、大型車両等でも同じです。
赤色の警告灯が点灯すると、オルタネーターが十分に電気を作っていない(発電量が十分ではない)か電気を作りすぎていることを示しています。
エアコンやウィンカーなどの電装系が不安定になる
オルタネーターの不調が発電の不良の場合、エアコンやウィンカーなどが電装系を動かすための電力が足りなくなって、動作が不安定になることがあります。
エアコンが効かなくなったり、ウィンカーが作動していなかったり、ヘッドライトや室内灯が暗くなったりすることがあります。
オーディオならば、ついたり消えたりするなど動作が不安定になる場合があります。
ハンドルが重たくなる
ハンドルが重たくなる症状が出た時にもオルタネーターの不調のサインです。
ハンドルが重たくなる=パワステが効かないということです。
車屋さんに行くと当たり前に「パワステ」という言葉が出てきたりします。
パワステはパワーステアリングの略で、運転する人のハンドル操作を補助してハンドルの動きを軽くしています。
モーターを利用してハンドル操作を補助しているのですが、モーターが電動式であることが多いです。
そのため、オルタネーターの発電不足で電力が足りず、正常に動かず、ハンドルが重くなる現象が起こります。
エンジンの振動が不安定になる
オルタネーターの発電不足になると、アイドリング中でもエンジンの回転が安定しません。
そのためエンジンの振動が大きくなったりエンストしそうになる場合があります。
エンジンがかからない理由は様々です。
ですが、ガソリンが十分に入っていて「昨日までいつも通り走行できていたのに」ということなら、オルタネーターの故障が考えられます。
車のエンジンをかけるには電力が必要です。
バッテリーに電気が溜まっていればかかりますが、オルタネーターが故障していると充電できないため走行中に充電できず、エンジンがかからなくなります。
オルタネーターの点検方法
オルタネーターは異音がし始めれば、なるべく早く対応しましょう。
そのため、エンジンをかけていつもと違う音がすると感じれば、ボンネットを開けてどこから音がしているかの確認をしてみましょう。
もしエンジン付近でオルタネーターからしていれば、車屋さん等に相談することをおすすめします。
車に詳しい人だと、オルタネーターチェッカーと呼ばれるものでオルタネーターの電圧を計測したりする人もいます。
カー用品店等で2,000円程度で販売されています。
持っていれば便利でとても安心できますが、通勤の移動で車を使用しているだけであったり、パートナーに任せているという方であれば、絶対に購入しないといけない品物ではないと感じます。
そのまま車屋さんで診てもらいましょう。
オルタネーターの寿命
オルタネーターの寿命は使用を開始してから、10年や走行距離が10万㎞と言われていました。
ですが、最近は技術の向上もあり走行距離が20万㎞を超えても使用し続けられるケースもあります。
明確に時期が来れば交換するという部品ではないため、年数や走行距離にとらわれず、走行中の音がいつも通りかを気にして車を使用するようにしましょう。
オルタネーターの寿命でよくあるケースは、部品の一部であるブラシです。
オルタネーターが電気を作る仕組みについて少し紹介します。
オルタネーターは内部が電磁石になっています。
エンジンが動くこととオルタネーターが連動しているので、内部の電磁石が回転することで電気を作ります。
金属製のブラシを通して電気を流し、中心部分にある電磁石を作動させているのですが、オルタネーターが動く=ブラシに部品が触れる回数が増えるため、ブラシがすり減ります。
オルタネーターの故障はブラシがすり減って、電力を伝えられずに作動しないというケースがよくあります。
ブラシが完全にすり減ると、電気をつくることができません。
そのため、エンジンがかけられなくなったり、走行中にエンストを起きたりします。
オルタネーターの不調はどこに相談する?
オルタネーターが不調だと感じれば、相談する場所は、主に3つあります。
「ディーラー」、「修理工場や地元の車屋さん」、「カー用品店」です。
それぞれのメリットやデメリットについて紹介します。
ディーラー
ディーラーとは自動車メーカーと特約店の契約を結んでいる正規販売店のことです。
車を販売することがメインですが、修理工場などを自社で持っていて、環境が整っていることが多いです。
ディーラーに持って行く場合、違うメーカーの車を持って行く人はいないでしょう。
該当するメーカーの車両を持って行くため、常駐している整備士は技術が高く、知識が豊富であることも多いことがメリットと言えます。
ですが、交換するパーツは純正品しか取り扱いが無いため、値段が高かったり、在庫の取り寄せに時間がかかったりする場合があります。
また持込の部品への交換であれば受け付けてくれません。
時間や予算に余裕がある方にお勧めです。
修理工場や地元の車屋さん
自宅近くの車の整備工場や修理工場、車屋さんでもオルタネーターの不調の相談や交換を依頼することができます。
修理工場などでは車のメンテナンス等を専門に受け付けているため、高い技術を持っていることが多いでしょう。
また、地元の車屋さん等でも信頼できる修理工場が取引先である事がほとんどです。
車のプロが取引している修理工場なので技術は確かでしょう。
相談してみることも一つの手段です。
修理工場や車屋さんでは、技術の高さも期待できますが、中古品やリビルト品などの持込部品でも交換の対応をしてくれたり、リビルト品を探してくれたりすることがあり、柔軟に対応してくれることが多いでしょう。
また、ディーラーよりも費用が安く抑えられる傾向にあるのも魅力の一つです。
ただし、依頼する先によって技術のレベルや費用は異なります。
まずは、電話で相談等をしてみたり、検索して口コミを見てみることがおすすめです。
カー用品店
カー用品店に依頼する場合は、全ての会社や店舗が行えるわけではありません。
オルタネーターの交換を行える技術を持ったスタッフや設備がない場合もあります。
また、持込の部品を受け付けてくれない場合もあります。
カー用品店での修理が選択肢にある人は、事前に対応ができるかどうかを確認しておきましょう。
オルタネーターは修理する?交換する?
オルタネーターが不調であることがわかれば、修理か交換もしくは車の買い替えの選択肢があります。
ここではオルタネーターの修理、交換の費用について紹介します。
オルタネーターの修理や交換をする際はオルタネーター代と工賃が必要です。
オルタネーター修理・交換の工賃について
オルタネーターを交換、修理する際の工賃の相場は1~3万円程度です。
「工賃」という言葉は車屋さん等では当たり前に使用されていますが、車の修理などをするときに必要な作業に対しての「技術料」です。
技術料よりも、手間賃と言う方がピンとくる方もいるかもしれません。
工賃には技術料以外に、工場の稼働費や設備機器の使用費等も含まれています。
業界で細かく定められている基準があるため、大体の相場は決まっています。
オルタネーター工賃は、車種によって車のボンネットを開けるだけで修理できるものや、機械を使用してリフトアップして交換しなければならないもの、他のパーツも分解して交換するものがあり、交換方法は様々です。
そのため、相場は1~3万程度と金額の開きがあります。
オルタネーター修理・交換について
オルタネーターの修理、交換はどのようなオルタネーターに修理、交換するかによって金額が変わります。
選択肢は以下の3つです。
- オーバーホール
- 新品へ交換
- リビルト品へ交換
それぞれの費用と修理や車を預ける期間についてまずは以下にまとめます。
| 交換費用 | 車を預ける期間 | |
| オーバーホール | 2~5万円程度 | 1日~3日程度 |
| 新品に交換 | 5~10万円程度 | 1時間~3、4時間 |
| リビルト品に交換 | 2~5万円程度 | 部品の有無で大きく変わる 1時間~5日程度になる場合もある |
オーバーホール
オーバーホールの場合金額は2~5万円程度です。
オーバーホールはオルタネーターに限らず車の他のパーツでも使用される言葉です。
オーバーホールは部品の分解をしてから、中の消耗部品や劣化している部品を新品に交換したり手入れして、再度組み立てる方法です。
必要な部品だけを交換したり修理したりするため、価格を安く抑えることができるのが特徴です。
キチンとオーバーホールを行い、手入れしたオルタネーターは新品同様に性能を発揮するため、安心して使用できます。
新品
新品への交換は安心ですが、費用は4つの選択肢の中で1番費用が高くなります。
新品のオルタネーターへの交換はメーカーの純正品で5~10万円程度です。
新品のオルタネーターでも外国製等ですぐに壊れてしまうものもあるため、保証内容も含めて検討することがおすすめです。
オルタネーターの交換は、車種によってオルタネーターが車両のどの位置に設置されているかによって交換時間は変わります。
前述の工賃の紹介と同様で、ボンネットを開けてすぐ交換できるものかや、車両をリフトアップしなけれければいけないものかによって作業時間も異なります。
リビルト
新品へのこだわりが無ければリビルト品でも十分です。
金額は2~5万円程度なので、新品の役半分です。
リビルト品は、車の修理を受け付けているところで取り扱っていたり、自分でフリマアプリやネットオークションで仕入れたりします。
車の修理屋さんがリビルト品を仕入れる場合は、取引先であるリビルト品屋さん等に連絡をして、在庫の確認をします。
もしなければ、新品のオルタネーターに交換になるケースが多いでしょう。
注意したい点としては、リビルト品の解釈は人によって様々です。
「中古の部品を分解し、手入れをして、新品同様の品質へ再生した部品」をリビルト品と呼ぶ人もいれば、ネットオークションやフリマアプリでは「取り外し前まで故障なく動いているもの(中古品)」をリビルト品と呼ぶ人もいます。
ネット上で仕入れる場合、写真だけで品質の判断をしなければならないため、純正品だったとしても、走行距離、使用年数、使用の状況等を踏まえて購入する必要があります。
また、リビルト品への交換をする場合、ディーラーや車屋さんが交換を受け付けてくれないケースがあります。
使用する場合は、部品の持込ができる修理工場や車屋さん等を事前に見つけて、お店に確認してから購入する方が無難でしょう。
また、絶対にリビルトのオルタネーターが見つかるかどうかはわかりません。
入手するまでに時間がかかる場合もあるため、運が良ければ使用できるということになります。
【まとめ】オルタネーターの不調のサインは音
オルタネーターの不調のサインはまずは音です。
エンジンを始動したときや走行中などにいつもと違う音(異音)がするなぁと感じれば、どこから音が出ているか確認してみましょう。
オルタネーターの場所は車種によってことなりますが、大体がボンネットの中に入っていてエンジンの近くにあります。
オルタネーターの修理を受け付けてくれる場所は、「ディーラー」「地元の車の修理屋さんや車屋さん」「カー用品店」です。
金額はオーバーホールか交換によって様々ですが、2万円~10万円程度です。